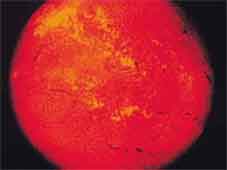ETについて
 TMA1と土星系との繋がりに疑いを持つものはいない。だがモノリスを建造した生物がそこに発生したと信じる学者もまたいなかった。生命が存在する場所としては、土星は木星よりさらに条件が悪い。とすれば、はるかな昔地球を訪れた生物は、地球外ばかりか太陽系以外のものかもしれない。多くの科学者は、にべもなくその可能性を否定した。これまでに設計されたディスカバリー号でもアルファーケンタウリまで到達するのに二万年銀河系内でちょっとした距離を進もうとすれば数百万年はかかる。もし将来、推進システムが改良されたとしても、やがては越えることのできない光の壁にぶつかるだろう。どっちにせよ、知的生物がすべて人と同じように短命だと考えるのはおかしい。千年の旅でもちょっと退屈する程度という生物だって存在するかもしれない。「高速は本当に越えられない壁なのか?」なるほど、特殊相対性理論、もうじき百周年がめぐってくるぐらい耐久力を示したが、だが、そろそろ三つの割れ目が現れてきている。アインシュタインを否定することはできなくても、彼をさけて通れるかもしれない「地球外の知的生物はどんな形態をしているのだろうか?」二つの対立するグループによる一方は、類人生物に違いないと主張し、他方は、人間と似ても似つかぬ生物と信じて疑わないのだ。前者の論点は二足二手主要な感覚器官が身体の最高部についていることが、必然的かつ理にかなったもので、これ以上優れたデザインを考えるのは容易でないといい。別の生物学グループは、人体は永劫の年月に偶然が作り上げた何百万もの進化の選択結果であり、と彼らは指摘した。これとは別のもっと異様な考えかたをする者がいたことをボーマンは思い出した。真に進化した生物が肉体組織を持つとは、彼らは信じていなかった。科学が進歩するにつれ、やがて生物は肉体という棲かから逃れ出る、病気や事故からたえずつきまとわれ、死えとみちびく肉体などないほうがよいのだ。かれらは金属やプラスチックの製品に取替え不死性をかちとるのだ。脳髄は有機組織の最後の残存物としてしばらくとどまり、機械の四肢に命令を送るのだ。最後には脳髄さえ消えてゆくのだ。意識の着床する場所として電子知性になる。知性と機械との対立はやがて完全な永遠の妥協で終るだろう・・・・しかしそれが究極だろうか?そしてその先にまだ何かがあるとすれば、それは神以外にあるまい。 TMA1と土星系との繋がりに疑いを持つものはいない。だがモノリスを建造した生物がそこに発生したと信じる学者もまたいなかった。生命が存在する場所としては、土星は木星よりさらに条件が悪い。とすれば、はるかな昔地球を訪れた生物は、地球外ばかりか太陽系以外のものかもしれない。多くの科学者は、にべもなくその可能性を否定した。これまでに設計されたディスカバリー号でもアルファーケンタウリまで到達するのに二万年銀河系内でちょっとした距離を進もうとすれば数百万年はかかる。もし将来、推進システムが改良されたとしても、やがては越えることのできない光の壁にぶつかるだろう。どっちにせよ、知的生物がすべて人と同じように短命だと考えるのはおかしい。千年の旅でもちょっと退屈する程度という生物だって存在するかもしれない。「高速は本当に越えられない壁なのか?」なるほど、特殊相対性理論、もうじき百周年がめぐってくるぐらい耐久力を示したが、だが、そろそろ三つの割れ目が現れてきている。アインシュタインを否定することはできなくても、彼をさけて通れるかもしれない「地球外の知的生物はどんな形態をしているのだろうか?」二つの対立するグループによる一方は、類人生物に違いないと主張し、他方は、人間と似ても似つかぬ生物と信じて疑わないのだ。前者の論点は二足二手主要な感覚器官が身体の最高部についていることが、必然的かつ理にかなったもので、これ以上優れたデザインを考えるのは容易でないといい。別の生物学グループは、人体は永劫の年月に偶然が作り上げた何百万もの進化の選択結果であり、と彼らは指摘した。これとは別のもっと異様な考えかたをする者がいたことをボーマンは思い出した。真に進化した生物が肉体組織を持つとは、彼らは信じていなかった。科学が進歩するにつれ、やがて生物は肉体という棲かから逃れ出る、病気や事故からたえずつきまとわれ、死えとみちびく肉体などないほうがよいのだ。かれらは金属やプラスチックの製品に取替え不死性をかちとるのだ。脳髄は有機組織の最後の残存物としてしばらくとどまり、機械の四肢に命令を送るのだ。最後には脳髄さえ消えてゆくのだ。意識の着床する場所として電子知性になる。知性と機械との対立はやがて完全な永遠の妥協で終るだろう・・・・しかしそれが究極だろうか?そしてその先にまだ何かがあるとすれば、それは神以外にあるまい。
| ヤスペタの眼 |
|
| ボーマンがはじめてヤスペタを観測したとき、例の奇妙な楕円形の輝く斑点は、土星反射光に照らされているだけで、半分は影にかくれていた、それは七十九日周期の軌道をゆっくり運行しながら、直射日光のなかに現れ出ていた。宇宙船がわずか五万マイルに近づき、ヤスペタが地球から見る月の二倍ほどの大きさになった。ディスカバリー号の主推進器が、最後のエネルギーの放出をはじめた。優秀なエンジンは何の誤りもなくその義務を成し遂げた、それは宇宙船を地球から木星へそして土星へとはこんできた。しかしそれが動作されるのは今回が最後なのだ。ディスカバリー号は惑星開発のあけぼの時代の記念塚として永遠に軌道を巡り続けるのだ。距離は千マイルから百マイル台に縮まった主推進器が噴射をとめるとバーニア【微調整するための小さなロケットエンジン】だけがディスカバリー号をそっと軌道に移すために活動する段階に入った。ヤスペタ、はほとんど静止した状態のまま、ゆっくりと近づいてきた。忠実なバーニアは最後のエネルギーを放出し、永久に活動を停止した。ディスカバリー号は、衛星の衛星になったのである。
|
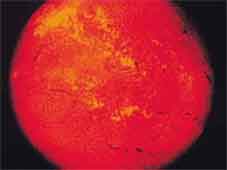 |
ビックブラザー
この星の表面には、二種類の物質しかないらしい。黒いほうは焼け焦げたみたいで、木炭によく似ている。白い区域については、まださっぱりわからない。境界ははっきりわかれていて、地表のディテールは何も見えない、液体ということも考えられる。何か重いガスかもしれない。三週目、また白い部分の上空にでた、だんだん内部に向かっている、なにかが見えてきた、望遠鏡で覗いてみる、例のものはビルディングに似ている・・・完全な黒色だ・・・表面はよく見えない、窓もなく、何の特色もない。ただ大きい垂直な石の坂だ。少なくとも高さ一マイルはあるだろう。「そうだ!月で見つかったものとそっくりだ!これは、TMA1のでっかい兄貴なんだ!。
実 験
三百万年間、土星の周囲を回りながら、運命の瞬間を待ち続けてきた。その建設のさい、一個の月が破壊されたその破片は今なお軌道を回っている。今、その待ち時間を終ろうとしていた。また一つの世界で知性が生まれ衛星のゆりかごから逃れようとしている。しかし彼らもまた血と肉からなる生き物であり宇宙の深淵を見上げるとき、彼らもやはり畏怖と驚異と孤独を感じるのだ彼らはさまざまな形態の生物と出会い、幾千もの世界で進化の働きを観察した。宇宙の夜のなかで、知性の最初のかすかな光がひらめき、消えていくのをいくたびに眼にしたことだろう。そして銀河系中で、精神以上に貴重なものを何処にも見出すことができなかったかれらは、いたるところでそのあけぼのを促進する事業をはじめた。彼らは星ぼしの畑の農夫となった、種をまき時には収穫を得た。そして時には、何の憐れみもなく除草しなければならないこともあった。調査船が一千年の旅を経てこの太陽の地を訪れたときには、巨大な恐竜はとうに滅びていた。それは凍りついた外惑星を通過し死にかけていた火星の砂漠の上空にひとときとどまり、やがて地球をみおろした。探検者たちが見出したのは、生命に満ちあふれた世界だった。彼らは何年もかかって研究し、分類した。知りたいことをすべて知ると、彼らは修正を加えはじめた。地上や大洋の多くの種の運命に干渉した、しかしそれらの事件のどれかが成功するかは、あとすくなくとも百万年待たなくては知ることはできないのだった。地球では氷河期が来たり、去っていった、氷河よりなおゆるやかなリズムで、銀河の文明の潮も満ち干をくりかえしていた。異様な、美しい、恐ろしい帝国が興っては滅び、知識を後に続くものに伝えた。そしていま星星の世界では、進化が新しいゴールを目指して進んでいた。地球を最初に訪れた探検者たちは、はるかな昔に血と肉の限界を感じはじめていた、機械が肉体を凌駕するとき、それは変化のときでもあった。はじめは頭脳を、次には思考そのものを、彼らは金属とプラスチックスの光り輝く棲みかに移しかえた。しかし機械生命の時代は急速に終った。彼らは空間構造そのものに知識を蓄え、凍りついた光の格子のなかに永遠に思考を存する方法を学んだ。やがて彼らは純粋エネルギーの生物に変貌した。今や彼らは銀河星の支配者であり、時すら超越していた。思うままに星ぼしのあいだを飛び、空間の割れ目のなかに沈みこむことができた。しかし神の様な力を得た現在でも、彼らは自分たちの出生地、消えさった海の軟泥をすっかり忘れてしまったわけではなかった。そしてなお、先祖たちが遠い昔に着手した実験の成果を見守っているのだった。
前 哨
船内の空気はすっかり濁ってしまって、このところずっと頭痛に悩まされている。あの事故以来浄化装置がうまく動いていない。今の軌道が傾斜しているので、TMA2からだんだん遠のいてしまう。まだ磁場が見つからない、今でも見えるのは二、三分のあいだだけで、そのうちに地平線に沈んでしまう、まともな観測ができなのでいらいらしてくる。スペースポッドには、着陸して帰船できるだけのデルダVはたっぷりある。EVAをして、物体を近くで観測したい。安全なようならてっぺんに着陸してみる。星の門(スターゲイト)は悠久の昔から太陽の方向に向けて異常の感覚をはたらかせていた。宇宙船は軌道に入り、奇妙な斑点を持ったつきの上空を低く回りはじめた。宇宙船は電波を放って話しかけた、一から十一までの素数を教え、もっと複雑な紫外線、赤外線、X線、星の門は応答しなかった、いうべきことは何もなかったからだ。長い間があり、何かが軌道を行く宇宙船から降下してくるのに気が付いた、それには記憶を探り、遠い昔に与えられた命令に従って、理論回路が決断を下した。土星の冷たい光のなかで、星の門は眠っていた力を呼びさました。
眼のなかへ
太陽も今では、それと見てわからないほど小さな星と化していた。星にしては明るすぎるが、直接その小さな円盤を見つめても、べつに苦にならなかった。熱はまったく送ってこない距離にあった。今の彼は、この何ヶ月か住み慣れた金属の家を、おそらく永遠に、離れようとしていた。もし帰ったとしたら、数ヶ月は生き延びながら正気をたもっていられるだろう、だが、それだけだ、冬眠システムにはそれをモニターするコンピューターがなくては役に立たない、四、五年後に救援が来るまでおそらく彼は生きていないだろう。fディスカバリー号は、今のところまだ、黒い空をまばゆい輝く星となって見えていた。降下のあいだは速度が上がっていたが、まもなく減速ジェットがはたらいた。黒い石板が、星ぼしを隠して地平線上に現れた。彼はポッドの向きを変え、最大噴射で減速した。そしてヤスペタの地表へと降下した。地球上でもこれほど単一な建物は少ない。正確に計測した写真で、それがおよそ二千フィート高さであることがわかった。その・・・なんと呼ぼう・・・その屋上の上には、岩一つ見えない、入り口らしきものも見えない。「・・おかしいなー・・・」ボーマンの声はとどまったようにとぎれた。恐怖をおぼえたのではなかった、文字通り説明できないだけだった。長さ800フィート幅200フィートの巨大な長方形の上にいた、ところが、それが、彼から遠のいていくように見えてくる、三次元の物体が見方を変えると、近い面と遠い面がいれかわって表面側が裏のように見えてくる、そんな目の錯覚とそっくりだった。それは平原からそそり立ったモノリスではなかった。屋上と思えたものは無限の深みに沈んでいた。その大きさはどこまでいっても小さくならなかったのだ・・・・。
ボーマンは、切れぎれの言葉をようやく言い終る余裕しかなかった。しかしそれは、九億マイル彼方、八十分未来で待ち構えている、管制官室の男たちにとっては生涯忘れることのできない一言になった。「なかは空っぽだ---どこまでも続いている---そして----信じられない---星がいっぱい見える!」
退 場
星の門は開いた。そして閉じた。
はかり知れぬほど短い一瞬、空間はねじれ、反転した。そしてヤスペタは、この三百万年間、常にそうであったように、ふたたび孤独になった---だが上空で主人をなくした、宇宙船が、その建造者たちにむかって、彼らが信じることも、理解することもできないメッセージを送り出しているほかは。
|
 TMA1と土星系との繋がりに疑いを持つものはいない。だがモノリスを建造した生物がそこに発生したと信じる学者もまたいなかった。生命が存在する場所としては、土星は木星よりさらに条件が悪い。とすれば、はるかな昔地球を訪れた生物は、地球外ばかりか太陽系以外のものかもしれない。多くの科学者は、にべもなくその可能性を否定した。これまでに設計されたディスカバリー号でもアルファーケンタウリまで到達するのに二万年銀河系内でちょっとした距離を進もうとすれば数百万年はかかる。もし将来、推進システムが改良されたとしても、やがては越えることのできない光の壁にぶつかるだろう。どっちにせよ、知的生物がすべて人と同じように短命だと考えるのはおかしい。千年の旅でもちょっと退屈する程度という生物だって存在するかもしれない。「高速は本当に越えられない壁なのか?」なるほど、特殊相対性理論、もうじき百周年がめぐってくるぐらい耐久力を示したが、だが、そろそろ三つの割れ目が現れてきている。アインシュタインを否定することはできなくても、彼をさけて通れるかもしれない「地球外の知的生物はどんな形態をしているのだろうか?」二つの対立するグループによる一方は、類人生物に違いないと主張し、他方は、人間と似ても似つかぬ生物と信じて疑わないのだ。前者の論点は二足二手主要な感覚器官が身体の最高部についていることが、必然的かつ理にかなったもので、これ以上優れたデザインを考えるのは容易でないといい。別の生物学グループは、人体は永劫の年月に偶然が作り上げた何百万もの進化の選択結果であり、と彼らは指摘した。これとは別のもっと異様な考えかたをする者がいたことをボーマンは思い出した。真に進化した生物が肉体組織を持つとは、彼らは信じていなかった。科学が進歩するにつれ、やがて生物は肉体という棲かから逃れ出る、病気や事故からたえずつきまとわれ、死えとみちびく肉体などないほうがよいのだ。かれらは金属やプラスチックの製品に取替え不死性をかちとるのだ。脳髄は有機組織の最後の残存物としてしばらくとどまり、機械の四肢に命令を送るのだ。最後には脳髄さえ消えてゆくのだ。意識の着床する場所として電子知性になる。知性と機械との対立はやがて完全な永遠の妥協で終るだろう・・・・しかしそれが究極だろうか?そしてその先にまだ何かがあるとすれば、それは神以外にあるまい。
TMA1と土星系との繋がりに疑いを持つものはいない。だがモノリスを建造した生物がそこに発生したと信じる学者もまたいなかった。生命が存在する場所としては、土星は木星よりさらに条件が悪い。とすれば、はるかな昔地球を訪れた生物は、地球外ばかりか太陽系以外のものかもしれない。多くの科学者は、にべもなくその可能性を否定した。これまでに設計されたディスカバリー号でもアルファーケンタウリまで到達するのに二万年銀河系内でちょっとした距離を進もうとすれば数百万年はかかる。もし将来、推進システムが改良されたとしても、やがては越えることのできない光の壁にぶつかるだろう。どっちにせよ、知的生物がすべて人と同じように短命だと考えるのはおかしい。千年の旅でもちょっと退屈する程度という生物だって存在するかもしれない。「高速は本当に越えられない壁なのか?」なるほど、特殊相対性理論、もうじき百周年がめぐってくるぐらい耐久力を示したが、だが、そろそろ三つの割れ目が現れてきている。アインシュタインを否定することはできなくても、彼をさけて通れるかもしれない「地球外の知的生物はどんな形態をしているのだろうか?」二つの対立するグループによる一方は、類人生物に違いないと主張し、他方は、人間と似ても似つかぬ生物と信じて疑わないのだ。前者の論点は二足二手主要な感覚器官が身体の最高部についていることが、必然的かつ理にかなったもので、これ以上優れたデザインを考えるのは容易でないといい。別の生物学グループは、人体は永劫の年月に偶然が作り上げた何百万もの進化の選択結果であり、と彼らは指摘した。これとは別のもっと異様な考えかたをする者がいたことをボーマンは思い出した。真に進化した生物が肉体組織を持つとは、彼らは信じていなかった。科学が進歩するにつれ、やがて生物は肉体という棲かから逃れ出る、病気や事故からたえずつきまとわれ、死えとみちびく肉体などないほうがよいのだ。かれらは金属やプラスチックの製品に取替え不死性をかちとるのだ。脳髄は有機組織の最後の残存物としてしばらくとどまり、機械の四肢に命令を送るのだ。最後には脳髄さえ消えてゆくのだ。意識の着床する場所として電子知性になる。知性と機械との対立はやがて完全な永遠の妥協で終るだろう・・・・しかしそれが究極だろうか?そしてその先にまだ何かがあるとすれば、それは神以外にあるまい。